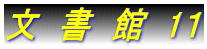
|
||||||||
 |
「幽 斎 殿 Ⅳ」 |
|
住吉大神(すみよしのおおみかみ)はみづからの消え切りの澄み切りである無量の光りであり給う、その光りに包まれることが、自分もまた消えていることであり、これを「全身全霊浄めらる」というのである。 「塩椎大神(しおつちのおおみかみ)に導かれて」とは、塩椎大神がみづから「私は無い」と消えてい給う、その消え切りに消え切り給うている、その聖なる輝きに浴することを意味するのである。 「無の門関に坐する」とは、無いものを無いとすること、すなわち、言葉、想念にて「無い」と言えるすべてのすべてを「無い」とすること、ただただその一筋でよいということなのである。 今朝目覚めた時、「ただ嬉し」という声が内よりひびいた。湧き出でた。そして同時に「その輝くひびき、声、湧き出ずるものも無い」のであった。 言葉、想念にて「無い」と言えるものすべて無し。 神無し、實相無し、内なし、神の国無し。光り無し。その無しも無し。その無しの無しの無しも無し。 「“無”を貫いたとき、そこに實相がある」と言えども、その「貫く」という意味は、その「實相」をも“無”とすることにあるのである。「“無”を貫いたとき、そこに實相がある」ということも“無い”と言えるからである。 “無し”と言えるすべてを“無し”として澄み切りの澄み切りに至る。その澄み切りの澄み切りも無いのである。澄み切りというものが自分の外にあるのではないのである。 實相というものが自分の外にあるのではないのである。神というものが自分とはなれて外にあるのではないのである。外にあるものは實相でもなく、神でもなく、澄み切りでもないのである。 “自性(じしょう)”ということ。 自性とは“在りて在る”なる自分無き渾(す)べての渾べてなる今ここなる神であり、天国にして極楽なるものであるのである。 “あるのである”こそが自性なるものなのである。 久遠崩るることなき今ここなる渾べての渾べてなるもの。渾べての渾べてなる、他なく相対なく、証明不要なるものであり、因縁超脱なるものである。 “吾が生くるは吾が力ならず、天地(あめつち)を貫きて生くるみ親のいのち”とは、自分は無く、神の一部ではなく、神そのものの全身がここに生き給うことなのである。この自性円満なる、すべてのすべてなるものの声として“一羽の雀(すずめ)と言えども、父のゆるしなくしては地に堕(お)つること能わず”と鳴りひびいているのである。道元はこれを“一切衆生悉有(いっさいしゅじょうしつう)は佛性(ぶっしょう)”と言い給い、釈尊は“山川草木悉皆成佛(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)、有情非情同時成道(うじょうひじょうどうじじょうどう)”と宣(の)り給うたのであり、大聖師谷口雅春先生は、“天地一切のものに感謝すべし”と単的に示されたのである。 現象無しの一転語による全宇宙の入れ換えによって拝される姿である。 “最早(もは)や吾れ生くるに非ず、神ここにありて、渾べての渾べてし給うなり”である。 神が今ここに天国し給い、神が今ここに極楽し給うているのである。神が“吾れ”し給うているのである。 「父の赦(ゆる)しなくば、一羽の雀といえども地に堕つること能わず」 もしも、父の赦しがなければ、悲しむことも、悩むことも、病いに罹(かか)ることも、憎むことも、恨むことも、死することも能(あた)わざるなり。それが能うのはただただそこに父のゆるしなるもののみが實在し輝き満ちているからなのである。 そして、その父は「吾が内にまします」のである。それ故に「赦すは吾れにあり」であるのである。 天地一切、萬事(ばんじ)萬物(ばんぶつ)萬象(ばんしょう)ことごとく「父の赦し」そのものであるのである。「一切衆生悉有は佛性」であり、「娑婆(しゃば)即(そく)寂光土(じゃっこうど)」であるのである。 「現象無し」とは、現象への限りなき父の赦しを意味しているのである。 「現象無し」とは、現象と見ゆるものはそのまま父の赦しの輝きそのものであることであり、「五蘊皆空(ごうんかいくう)」とは「五蘊皆光」であるのである。 「赦すは吾れにあり」とは、赦す側、創造する側、生み出す側にいることを意味するのである。 音を生み出す側のよろこびに立つまでは、どんなに音からよろこびを得ようとも、“これでよい”という完全なる充足は味うことは出来ないのである。景色でも、景色から何かを、よろこびを得ようとして、景色に求めている間は充足は得られないのである。景色を生んでいるよろこびこそ、最後なるよろこびであるのである。 「他(隣人)を己れの如く愛せよ」とは、神を己れとして愛せよ、ということであり、實相世界を己れとして愛せよ、ということであり、天国極楽浄土を己れとして愛せよ、ということであり、釈尊を己れとして愛せよ、ということであり、キリストを己れとして愛せよ、ということであり、大聖師を己れとして愛せよ、ということである。 “己れとして”とは、己れの展開として、それのひろがりとしてということであり、“愛せよ”とは観ぜよ、ということである。 「他のよろこびを自分のよろこびとせよ」とは、他としてあらわれた自分を、神なるよろこびそのものとして、その實在の相(すがた)を観ぜよ、ということである。自分をとりまく天地一切のもののよろこんでいる姿は“自分がよろこんでいる姿である”ということである。自分がその人のよろこんでいる姿として展開しているということである。 「十方世界光明遍照(じっぽうせかいこうみょうへんじょう)、吾が全身光明遍照」と唱える。しかし、十方世界も吾が全身も「ひとつ」であるのである。 十方世界も吾れであり、吾れも吾れである。これ十方世界を己れのごとく愛し、生くることであるのである。 「神、光りあれと言い給いければ光りありき」と聖書には示されているのである。光り以前を神と言い、光り以前を“在りて在るもの”というのであり、真空にして妙有なるもの、幽の幽の幽なるものというのである。光りは無いのである。 「日々大祭(たいさい)」である。大祭とは、吾が内に一切があることを拝むことにほかならないのである。外は無いということである。無いものを無いと知るのはまことの自分であり、實在(ある)ものを實在(ある)と知るのもまたまことの自分であるのである。大祭は自分の中で行われるのである。 「天地(あめつち)のはじめのとき、高天原(たかあまはら)に成りませる神の名(みな)は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高御産巣比神(たかみむすびのかみ)、神産巣比神(かみむすびのかみ)、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこじのかみ)、天之常立神(あめのとこたちのかみ)、国之常立神(くにのとこたちのかみ)、豊雲野神(とよくもぬのかみ)。これら七柱の神は独神(ひとりがみ)なりまして、身(みみ)を隠し給えり」と『古事記』には記されているのである。独神(ひとりがみ)とは絶対神ということであるのである。 天地一切萬物は「山川草木国土悉皆成佛、有情非情同時成道」と釈尊の拝まれたごとく、ことごとく佛であり、神である故、天地一切萬物はことごとくそのまま独神(ひとりがみ)すなわち絶対神であるのであって、身(みみ)を隠し給いて、みづからの消え切りの澄み切りの聖なる輝きそのものなのである。高天原は遠くにあらず、「吾が内に、今ここに、吾れとして」あるのである。 高天原も龍宮本源も自分自身のことであったのであり、天地一切萬物ことごとく、そのまま高天原であり、創造の本源、龍宮本源そのものであったのである。これが「はじめのはじめ」の消息であり、無の無のそのまま無しの無しの澄み切りにして、真空にして妙有(みょうう)なる消息であるのである。 神癒祈願お申し込みのお一人お一人が独神(ひとりがみ)すなわち絶対神にましますのである。絶対神とは完成なる、成就そのものなることを意味しているのである。 實相世界の、神の無限の智慧の海、愛の海、生命の海、供給の海、よろこびの海、調和の海の六つの御徳の海もそれぞれそのままに絶対神すなわち独神(ひとりがみ)であり給いて、身(みみ)を隠し給うて、澄み切りなのである。 それ故、この六つの御徳は一つなる澄み切りの「生かす力」なのであり、それが流れ入って、吾れに満ち満ちて不透明なる肉体が無色透明に澄み切るのが神想観であるのである。 斯くの如く、斯くの如くして、生長の家の聖典の一言一字はことごとく独神(ひとりがみ)にましまして身(みみ)を隠し給いて、聖の聖なる、はじめのはじめなる澄み切りの輝きにましますのである。 高天原に成りませる「七柱」の神は「無限柱」の神を意味しているのである。七は完成、完全をあらわし、完全は無限をあらわしているのである。その無限柱の神はことごとく独神(ひとりがみ)にましまして、無限柱の神ことごとくが絶対そのものにましますのである。無限とは「すべて」をあらわして、すべてのもの、天地一切萬物がそのまま、ことごとく独神(ひとりがみ)すなわち絶対神であることであるのである。 天地一切萬物ことごとくを独神(ひとりがみ)すなわち絶対なるものとして観ずることが天地一切感謝であるのである。感謝とは絶対価値の判定である、とはこの意味でもあるのである。 神癒祈願における人型の「實相円満」とは、祈願を受ける人、その申込書が独神(ひとりがみ)にましますことを意味しているのである。 神の一人子とは、神なる一人子であり、神は独神(ひとりがみ)にましますが故に、その子は独子(ひとりご)であるのであり、独子(ひとりご)とは絶対なる子ということであるのである。 絶対なる子が一人子なのである。 浄まるとは、あるべきものがあるべき相(すがた)にあることである。それ故、天地一切萬物ことごとくは独神(ひとりがみ)であるのであれば、その独神(ひとりがみ)であることを観じ、認め、生くることが浄まっていることなのである。独神が独神していることこそが浄まっていることにほかならないのである。 「畏(かしこ)くも宇宙の大神イザナギの命(みこと)、筑紫(つくし)の日向(ひむか)の光明遍照の實相の世界に身潔(みそ)ぎ祓(はら)い給う」とは、イザナギの大神が「筑紫の日向の光明遍照實相世界」し給うことなのである。 “聖なる自己よ”とみづからがみづからに呼びかけ得るところのもののみが“吾れ神なり”“神吾れなり”と言い得る實相なのである。 独神(どくしん)とは独身(どくしん)であり、吾れすなわち聖の聖なるものであるのである。“今を生きよ”とは今、“聖なる自己よ”と吾れ自身に吾れ自身が言い得てよいということであるのである。ただ一つ肯定し得るもの、自己礼拝し得るものは聖の聖なるもののみであるのである。“聖なる自己よ”とは“神なる自己よ”ということにほかならないのである。 リンゴはリンゴを生くるのみ。リンゴがリンゴらしからぬ相(すがた)をあらわすのは、自分がリンゴ以外のものであると想うた時のみである。 人間が善を生きることの出来るのは、ただただ人間が善そのものであることを知ることによってのみである。善のみ善を生きることが出来るのである。本来善そのものである實相を遠慮しないことである。 現象を無として超えた時、そこに實在があり、神があり、天国がある。「そこ」にと想う時、それはまだ本当ではないのである。「そこ」を「ここ」に持ち来たすことが必要なのである。斯く『真理の吟唱』は唱えているのである。 それでは、「そこ」を「ここ」に持ち来たすにはどうすればよいのであるか。それは「そこ」は無いということを知ることによってなのである。「そこ」すなわち、實在、神、天国無しとし、自分に対するすべてが無いとき、すでに自分は無いのである。自分が無いとき全べて無く、「そこ」なく、「ここ」のみが在りて在るのである。神、佛、實在、天国を自分と相対する外のものであると想ってはならないのである。すなわちそのような“神無し、實相無し、天国無し”“「そこ」無し”とすることである。「そこ」を無しとしたところを「ここ」というのである。 「ここ」とは在りて在る渾べての渾べてであるのである。「ここ」とは今であり、今とは吾れ無き吾れ、神なき神、實相なき實相、澄み切りである。 一切の外なるもの、外そのものが無いことを知ることこそが天之岩戸(あまのいわと)を開くことであるのである。 外なるものが無いとき、内なる天照大御神のみ渾べての渾べてとなるのである。渾べての渾べてであることが全開きであり、天之岩戸無しなのである。これが“住吉大神、宇宙を浄め給いて天照大御神出でましぬ”ということなのである。これが天之岩戸を全開きにしたことであり、岩戸のある山そのものが無くなって、天照大御神のまる裸があるのである。このまる裸をたたえたのが、アメノウズメのみことの裸おどりであったのである。天照大御神が渾べての渾べてであり、この渾べての渾べてなるものの発見が、「ここ」なるものの発見であり、吾れの吾れなるものの発見であるのである。 新しき皮袋に新しき酒をつぐこと。 即ち、實相は完全である、けれども現象は不完全であるのである。 現象は不完全であるけれども實相は完全である、という言い方の順序を止めよ。 實相は完全である、ですべては完成し、完結しているのである。不完全な現象というものは遊びであるのである。 “神の子”というと言えども、“神”であること、“神”が先きであり、それで渾べての渾べてであり、こと終れりであり、完成完結なのである。“子”であることは遊びであるのである。 「真空妙有」「無一物中無尽蔵(むいちぶつちゅうむじんぞう)」とは、真空あるいは無から一切が出て来るということではないのである。真空、無そのままに今、ここに妙有なるものがあり、無限なるものであるということである。「自分は無(ゼロ)である」ということを味うと同時に無限、妙有なるものを味うのである。 「真空妙有」とは、真空と妙有を同時に味うことなのである。真空ということと、妙有ということが別時別処であるのでもなければ、真空というものが先づあって、そこからある時間の経過を経て、妙有が生れ出るのではないのである。 無にして一切であるということは、無と一切が同時に現成し、同時に味えるということなのである。無と有とが罣礙(けいげ)せず、まことに渾べての渾べてなのが妙有ということであり、入龍宮(にゅうりゅうぐう)不可思議(ふかしぎ)と言わざるを得ないのである。 「無にして絶対」とはこのことの消息なのである。はじめなきはじめにして終りなき終りなる久遠の今の消息もまたこれなのである。 目的のための、目標のための、象徴としての言葉ではなく、言葉が神であり、実体であり、渾べての渾べてであるのである。 言葉がシンボルである、という時代は實相なるものの発見によって終りを告げたのである。 言葉は神である、とは、神でないものは言葉ではないということである。神である言葉は完成なる言葉であり、成就そのものである言葉であるのである。 「こと終れり」とは「こと完成せり」ということであるのである。完成なる言葉こそ、成就そのものであるのである。成就とは完成を意味しているのである。 言葉それ自体が神であり、渾べての渾べてであり、完成そのものであるのである。このような言葉を霊というのである。 神はすべてのすべてであり、それ故に神は自分なるものであり、自分が言葉であり、一切である自覚によって発せられる時の言葉が霊なるものであり、神であり、成就そのものであるのである。すなわち「こと完成せり」であるのである。 「上より来たるもの」とは渾べての渾べてなるものより発せられたる成就なる言葉であるのである。 天孫降臨(てんそんこうりん)とは、言葉なるもの、完成なるものの降臨であるのである。天孫、邇々藝命(ににぎのみこと)の降臨とは、「コトバ」の降臨を意味しているのである。すべてのいのちある言葉は、この降臨のすがたとしてあるのである。 完成なるものの発する言葉こそ神である言葉であり、天孫なるものの本体は神であり、言葉であるのである。『聖典』と言わざるを得ない言葉はすべて天孫の降臨であるのである。 神なる言葉とは光明なる言葉であり、光明なるものとは一元なるもののひろがりとしての言葉であるのである。 「自在」とは自(みづ)から在るところのものである。すなわち“在りて在る”ところのものであって、現象的自我行(ぎょう)の如何なるものによっても証明され、証拠立てされる必要のないものなのである。 自(みづ)から在りて在るところのものこそ、まことの自性的なるものであり、“only one”なるものなのである。“ほかには無いものである”という「ほか」というものが無いということによって成り立つところの個性的なるものではないのである。そのようなものは他をまつところの存在にすぎないのである。 自在とはそれみづから在りて在るものであり、それみづから渾べての渾べてなるものであり、「他」そのものの存在しない、それのみであるものこそ“only one”なのである。 したがって“only one”なるものとは、陰陽のはたらき、生み出し以前の存在でなければならないのである。それが“独神(ひとりがみ)”なるもののすがたであり、それは渾べての渾べてであり、観るものと観られるものとの相対以前の消息であり、“観る”“観られる”ことを超越していることを称して“身(みみ)を隠し給いき”というのである。“観るもの”がなければ無いということであり、これを幽の幽とも称し奉るのである。「三界に身を現さず」という言葉もこの消息であるのである。尽十方無礙光如来(じんじっぽうむげこうにょらい)とは、すべての方向を尽して、すべてのすべてであるが故に、相対的にこれをはなれて観るものなきが故に、身(みみ)を現すことなし、であるのである。それは観るもの自体の死に切り、消え切りの消息をも意味しているのである。 「中心帰一」の中心とは円の中心のように想われ、円そのものの面積よりも狭く小さなもののようにとらえられるかも知れないが、至大無外(しだいむがい)至小無内(ししょうむない)である中心ほど広いものはなく、渾べての渾べてであるものは無いのである。 この中心なるものは絶対なるものであり、遠心に対する相対の中心ではなく、在りて在る、渾べての渾べてである、それ自身みづからそれであるところの中心なのである。 中心は一切であり、中心の内に遠心があるとも言えるのである。中心の中に天地一切萬事萬物があるとも言い得るのである。即ち中心は神であるのである。 新しきものとは、古くならないものでなければならないのである。自(みづ)からに甦(よみが)えりを自性しているものでなければならないのである。例えば生きている草木は常に新しき芽を生(ふ)いて新しさそのものであり、毎年同じ葉や花を生(ふ)いても人は決して“マンネリ”だとか“もう飽きた”とかは言わないのである。 まことに新しきものは個性的なものであって、そこにしか、そこでしか有り得ないものであり、外(ほか)の何ものによってもかわりをつとめることの出来ないものなのである。すなわち、ひとの真似をしないことなのである。悟りについても、体験の発表を聴くのも、その人の真似をするためだけであってはならないのである。たとえ、釈尊やキリストのことであってもその真似であっては、そこに新しきもの、古くならないもの、甦えりなるものを味うことは出来ないのである。 人は何によって真似をするのであるか。それは五官によってキャッチされたものに反応することによってなされるのである。それ故に生長の家では神想観すなわち五官の世界を去ることが最根本の行持となっているのである。 “花咲かじいさん”の話だろうと、“舌切りスズメ”の話だろうと、隣りのおじいさんおばあさんは真似ばかりしているのである。その真似した分だけ自分を失って、自分が自分であり、みづからに甦えりすなわち新しさをそなえている“いのち”なるものの姿から遠ざかっているのである。 どんな話や体験談を聴いても“いつもそうだろうか?”“自分の場合は別である”という想いは残るのである。それは実は“いのち”なるもののかけがえのない、まことの個性なるものの輝きであるのである。それ故、やみくもにひとの体験を聴いて“信じられない”と言って失望するにはあたらないのである。そのような時はむしろ自分の中の輝きに向って祝福の念を起すようにする方がいのちの流れに対して自然なことなのである。 神は偉大なる個であり給い、個性そのものであり給うのであれば、“そのまま”“素(そ)のまま”“もとのまま”が偉大なる個性であることなのである。“そのまま”の反対は“わがまま”ということである。“わがまま”であることと“そのまま”なる個性的であることとは全く別のことなのである。自分なる吾れなる“わが”ということが無いのが“そのまま”であることであり、個性的であることなのである。 「天地(あめつち)のはじめの時、高天原(たかあまはら)に成りませる神の名(みな)は………」と『古事記』は歌っているのである。天地のはじめが渾べての渾べてであり、天地のはじめのみがあるのである。高天原に詰りまして成りませる七柱の神は独神(ひとりがみ)なりまして身(みみ)を隠し給う、とは、実は独神(ひとりがみ)は絶対神であり給い、天地のはじめそのものであり給い、七柱の神以外、天地のはじめ以外のものが無いこと、すなわち、自(みづ)から死に切りの消え切りであることなのである。天地のはじめ以降の神々が却って身(みみ)を隠して消えているのである。 それ以外なく、それのみすべてのすべてであることこそが身(みみ)を隠し給うていることなのである。それ以外“無い”ということが身(みみ)を隠し給うということなのである。七柱の神以降の神々はすべて“無い”のである。ただただ“無い”がままにあり、“ある”がままに“無い”のである。それ故に七柱の神以降はすべて“降る”ように何の力も要らずして生じているのであり、生じているままに“無い”のである。“無い”とは、言葉あるいは想念にて“無い”と言えるすべてのものをいうのである。“無の門関”想うべし。 高天原に天地のはじめのとき鳴りませる神は七柱あり、独神(ひとりがみ)にましまして、絶対神にして身(みみ)を隠し給うているということは、高天原それみづからも身(みみ)を隠し給いて澄み切りにましますことを意味しているのである。 身(みみ)を隠し給うて澄み切りのままに展開することを“自(おのづ)から”というのである。自(おのづ)からなる、天地の創造がここにあり、それがそのまま“光りあれ”というおのづからなるコトバの展開であるのである。 實在宇宙の展開は“おのづから”なのである。“おのづから”なる展開とはまた、その展開そのものがみづから“無い”と消え切りであることなのである。創造(つく)るものなくして創造り、創造られるものなくして創造られ、生むものなくして生み、生み出されるものなくして生み出されているのが“おのづから”なるものの消息であるのである。 神は天地創造されつづけていても、そこには何らの力(りき)みも相克の姿もないのである。“私は未だかつて何ものも創造らない”という安らかそのものであり給い、常楽そのものであり給うのである。その意味において神は“静か”であり給い、はじめから“こと終れり”すなわち“こと完成せり”であり給うのである。 高天原に成りませる七柱の神は独神(ひとりがみ)にましまして身(みみ)を隠し給えりとは、天地一切萬物がことごとく独神、すなわち絶対神にして、渾べての渾べてであることなのである。渾べての渾べてであり、それのみが渾べての渾べてであることが身(みみ)を隠し給いきなのである。 萬物が独神(ひとりがみ)であり、渾べての渾べてであることが澄み切りの大調和であることなのである。 神による天地創造は無いのである。神も天地も創造もすべてみづからの消え切りの澄み切りであるのである。これが幽の幽に隠れましていることなのである。イザナギ、イザナミの国生みもまたこの意味において無いのである。聖経『甘露の法雨』に書かれていることも聖経そのものも無いのである。神も神の天地創造も無いのである。神は“私は何ものをも創造(つく)らない”とみづから消え切りであり、天地もまたみづからの消え切りであるのである。神は三界に身をあらわし給うことなしである。天地そのもの、三界そのものを創造り給わないのであり、みづからも消え切りであり、澄み切りであり給うのである。 「高天原」以前に還るとき、神生みがはじまるのであり、国生みがはじまるのである。 コトバは神である。それ故、コトバが発せられ、生み出されることは神生みであるのである。 “絶対の神”という言葉が発せられるとき、絶対の神がそこに生まれてい給うのである。「高天原」という言葉が発せられるとき、そこに「高天原」が生れているのである。「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高御産巣比神(たかみむすびのかみ)……」と七柱の神を唱えるとき、そこに七柱の絶対神が生れてい給うのである。 それ故に、吾れの吾れなるものの発するコトバによって神から生れ給うということは、神のいのちは吾がいのちであり、神のみ心は吾が心であるということなのである。 「神の心動き出でてコトバとなれば、一切の現象展開して萬物成る」(『甘露の法雨』)というその「神の心」とは吾が心であるのである。「吾が心生れ出でて神のみ心となり給う」ているのである。これらすべては「神生み」ということに含まれることなのである。その意味において「神想観」は神生みの行であることにおいて荘厳きわまりなき神行であるのである。「神示」もまた神生みであり、聖経『甘露の法雨』、聖典の読誦もまた神生みの荘厳なるすがたであるのである。その神が天地陰陽となり、展開し給うているのである。自分の自分なるものが展開して神のみ心となり、みいのちとなっているのである。「招神歌」は神生みそのものであるのである。その意味において「神のみいのちわがいのち、神のみこころわがこころ」(「神と偕に生くる歌」)なのである。 今、吾が内にまことのまことなる、神の神なるものの復活を想うのである。神の神なるものとは“絶対なるもの 即ち神を生み給うところの神”という意味なのである。絶対なるものを絶対なるものとして名付けるものあり。 |